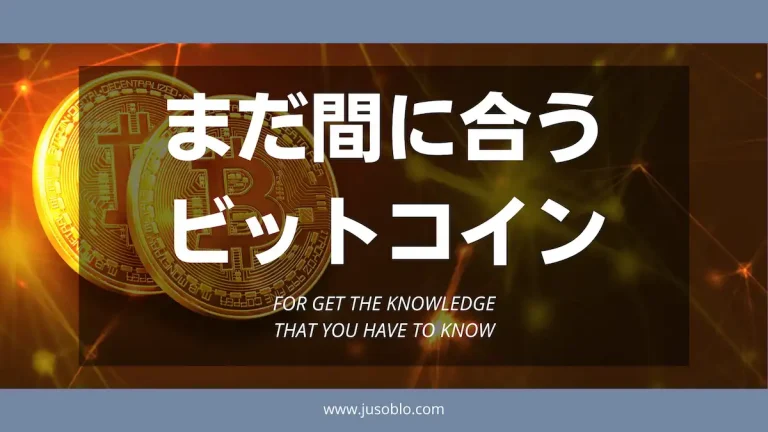こんにちは、jusonです。
・ブロックチェーンって何?
・ビットコインに問題はないの?
こんな疑問を解決します。
本記事はを読めばビットコインについての基礎知識が得られます。
ビットコイン投資がこれからという方におすすめです。
それでは行きましょう!
ビットコインって何?
ビットコインはいつどこで生まれた?
「サトシ・ナカモト」を名乗る人物が2008年11月に発表した暗号理論に関する論文が出発点です。
ただ、単独で開発したのではなく、開発者のオープンコミュニティの中で「サトシ・ナカモト」が提唱したブロックチェーン技術に興味を持った人たちが分担してコードを書き徐々に現在の形に近づいてきました。
こういった経緯から、「ビットコイン=怪しい」といったイメージがあるのかも。
ビットコインは誰が運営している?
ビットコインには運営主体はなく関係者による話し合いで運営されています。
とはいえ、ステークホルダー(利害関係者)から見ると、実質的な運営主体は「開発者コミュニティ」ということですね。
ステークホルダー ※影響度上位から記載
- 開発者コミュニティ
初期の開発から携わってきたメンバー - マイニング業者
取引を承認し、ビットコインを新たに発掘する採掘者 - 取引所
「交換」「保管」「送金」などの取引を仲介する取引所 - サービス事業者
ビットコインを貸し出すレンディングサービスやECサイト - エンドユーザー
個人投資家、機関投資家、企業
ビットコインの6つの顔
ビットコインは「仮想通貨」の一つですが、そうしたくくりはビットコインの一面でしかありません。
ビットコインは主に次の6つの顔があります。
- 【仮想通貨】
- 【デジタル通貨】
- 【国際通貨】
- 【分散型通貨】
- 【暗号通貨】
- 【暗号資産】
それぞれ説明していきます。
1【仮想通貨】実体の無いバーチャルなお金
Web上のバーチャルな専用財布「ウォレット」で管理する、実態のないバーチャルなお金です。
クラウド上に保管してあるのでスマホのデータを完全に消去しても失われる心配はありません。
2【デジタル通貨】持ち運び自由の電子データ
ビットコインは電子データにすぎないので、どれだけ金額が大きくなってもかさばる心配はありません。
自分のPCやスマホにダウンロードされているわけではなく、取引所のクラウド上に預けっぱなしになっているイメージですね。
3【国際通貨】国に属さない通貨
ビットコインは特定の国や中央銀行となる組織が発行していないので、国によるコントロールを受けません。
金利や景気の影響を受けないので、世界中どこでも同じように使うことができる、真の「国際通貨」と言えます。
4【分散型通貨】民主的な運用とP2Pネットワーク
ビットコインはネットワークに参加しているメンバーが互いに承認し合うことで「取引の正しさ」を担保しています。
それを支えているのがP2Pといわれる分散処理システムです。
一元管理ではなく相互の承認によって管理されている「民主的な通貨」であり、中央集権型のサーバー方式とは真逆の「分散型通貨」といえます。
5【暗号通貨】暗号を解く鍵がないと送金できない台帳技術
ビットコインは「電子署名」という暗号技術によって所有者に無断で送金ができません。
また、過去から現在までのすべての所有者が、ブロックチェーンと呼ばれる「台帳」に記録されています。
これによりマネーロンダリングのような不正操作に悪用されにくいメリットがあります。
6【暗号資産】投資対象として魅力あふれる資産
ビットコインは現金の代わりになる「通貨」という面がある一方、将来値上がりして儲かるはずと「資産」としての価値が認められています。
なんで資産価値がある?
まず前提として、「資産」とは次のように定義できます。
- お金を出して買えるもの
- 長い期間価値が無くならないもの
- 将来価値が増えると期待されるもの
ビットコインが資産と認められているのは、将来の値上がりする期待値が高いからです。
また、ビットコインには次の価値(信用)があるため資産となり得るのです。
誰も偽造・改変できない
ビットコインには「ここの取引記録を相互に承認する仕組み」があって、「だれもそれを偽造したり過去にさかのぼって改変したりすることはできない」と信じているからこそ、そこに信用が生まれます。
特定の国や人の支配を受けない
ビットコインは特定の国や企業によって発行されるものではないため、国の思惑に左右されることなく、安定的に流通量が増えていきます。
有限であること
ビットコインは予め上限があり、2100万枚発行された時点で、打ち止めになります。計算上は2141年にすべてのビットコインが彫り尽くされる予定です。
つまりビットコインも金と同じように、「希少」だからこそ価値が認められています。
他の資産との違い
ビットコインは日常的に使う「通貨」という側面よりも、「資産」としての側面が強いとされています。
似たような投資先との主な違いは次のとおりです。
銀行預金との違い
銀行預金は「利子」が付きますが、暗号資産にはありません。
また、銀行が潰れた場合最大1000万まで保証されますが、暗号資産取引所が潰れると預けていた資産は返ってきません。
ドル、ユーロとの違い
ドル、ユーロ、円は国の信用が崩壊すると通貨は暴落します。
ビットコインの価値は国ではなくそれを支えるアルゴリズムの信用で成り立っています。
ブロックチェーン技術のこれから伸びるという期待が今後の値上がりするという読みを支えています。
FXとの違い
FXのレバレッジは最大25倍、ビットコインは(日本では)2倍と定められています。
通常の通貨ペア(ドル円、ユーロ円)などは流動性が高いが、ビットコインとドル、ビットコインと円の流動性はまだ低い。
株や投信との違い
株と投信は企業の成長に対する投資ですが、ビットコインは組織ではなくテクノロジーの成長に賭ける投資といえます。
電子マネーとの違い
「デジタル通貨」のビットコインと、「デジタルなお金」の電子マネーの違いは次のとおりです。
物理的なカードがない
ビットコインに物理カードはなく、取引所が提供する「ウォレット」のアプリをスマホに入れて使います。
お店側が対応すれば支払いはビットコインの送金と同じです。
ビットコインに国境はない
電子マネーは海外に行くと使えませんが、ビットコインには国境がないのでニューヨークに居るときでも日本国内と同じように利用できます。
代替手段
電子マネーは「円」や「ドル」の代替手段でしかない。
ビットコインは円やドルと交換可能な「お金」そのものです。
ビットコイン価格の変動要因は?
ドル円相場に影響を与えるのは、アメリカ雇用統計や、日本のGDP速報があります。
それ以外にもFRB(連邦準備制度理事会)議長や日銀総裁の発言などが必須の情報ですよね。
これに対しビットコイン価格の変動要因はこちらです。
- 各国のレギュレーション(規制)の動向
- 大口保有者の発言
- SDGs(持続可能な開発目標)に沿っているか
- 法定通貨化
- 半減期
それぞれ説明します。
各国のレギュレーション(規制)の動向
ビットコインに関する規制は国ごとに違うので新しいローカルルールが発表されるとビットコイン価格に影響します。
例えばマイニング業者のたくさんいる中国で規制が強化されるたびにビットコイン価格が急落するという一連の流れがあります。
大口保有者の発言
資金力が桁違いのファンドや企業がビットコインを購入すると金額の単位が大きいだけに相場に大きく影響します。
大口保有者リストは「Bitcoin Rich List」で検索するといくつかのサイトで確認できます。
今では中国よりもアメリカの動向に注目が集まっています。
SDGs(持続可能な開発目標)に沿っているか
ビットコインのマイニング(承認作業)には高度な処理能力を持つ専用マシンがフル稼働していて、消費される電力量も膨大です。
ビットコイン大量保有者に機関投資家が増えたことで、社会的要請に敏感な彼らが脱炭素を推進する企業を支援する「グリーン投資」を本格化しています。
そのため、SDGsにどれだけ沿っているかが価格変動要因になるのです。
法定通貨化
2021年9月にエルサルバドルが国家として初めてビットコインを法定通貨として認めました。
経済が弱く自国通貨が持てない他の中南米諸国も関心を寄せている。
今後こうした国々がビットコインを法定通貨と認めていくことになると、基軸通貨のドルの覇権を揺るがしかねません。
今後アメリカがどう対抗するのかも注目です。
半減期
ビットコインの半減期はオリンピックイヤーの2016,2020,2024年と4年毎に訪れます。
ビットコインの半減とはマイニング報酬が半分になることを意味します。
なぜ半減期が必要かというと、コンピュータの処理能力は年々向上するので、マイニングのコストはそれに応じて減っていくと考えられているからです。
ビットコインに上限がある?
ビットコインは発行枚数の上限が2100万枚と決まっています。
上限が設けられている理由は次の通り。
- 有限だからこそ価値がある
- 流通し過ぎて価格の暴落(ハイパーインフレ)などの心配がない
とはいえビットコインが始まった2009年からわずか12年で全体の89.5%以上がすでに掘り出されています。
しかしながらビットコインが彫り尽くされるのは2141年とされており、まだ100年以上も先の話です。
今後すぐに上限に達しない理由は、ビットコインには最小単位が決められているからです。
最小値は、「1satoshi=0.000000001BTC」と決まっています。
半減期を繰り返していくと、マイニング報酬はやがて1satoshiを下回ります。
ここでビットコインの新規発行はストップします。
取引所の役割
ビットコイン取引において、いつでも交換可能な「場」を提供しているのが取引所です。
主な役割はつぎの3つです。
- ビットコインと円やドル、他の仮想通貨と交換する場の提供
- ビットコインをユーザーに代わって保管する
- ユーザーの支持に従ってビットコインを送金する
「取引所」と「販売所」の違い
同じ暗号資産交換業者が「取引所」と「販売所」を運営していることが多く、両者には明確な違いがあります。
紛らわしいのですが、実際に取引を始める際にはこのどちらかを使うことになるので、必ず違いについて抑えておきたいところです。
主な違いは次の通りです。
取引所
・希望価格で取引する相手がいなければ売買不成立
・ヤフオクやメルカリと同じイメージ
・売買を仲介するだけで手数料は安い
販売所
・販売所が売値、買値を決めており、希望価格での取引はできない
・取引相手が見つからず、売れない、買えないという事態はない
・売値、買値に差「スプレッド」が設けられている
・これが販売所の取り分、つまり実質的な「手数料」
ユーザーとして一番大きく影響がある部分は手数料でしょう。
これらの違いを知らずに、感覚的に分かりやすい販売所で購入してしまうと無駄な手数料を払うはめになります。
ビットコインは「取引所」で購入しましょう。
対比表
| 取引所 | 販売所 | |
| 取引相手 | ユーザー同士 | 販売所⇔ユーザー |
| 売値、買値 | ユーザーが決める | 販売所が決める |
| 取引のタイミング | 相手が見つからなければ不成立 | 買いたいときに買える
売りたいときに売れる |
| 手数料 | 安い/無料 | 購入価格ー売却価格=スプレッド(割高) |
| わかりやすさ | 「成行」や「指値」といった株と同様の売買知識や、多少の慣れが必要 | 価格が決まっており直感的に分かりやすい |
ブロックチェーンって何?
ビットコインを支える根幹となる技術が「ブロックチェーン」です。
ビットコインの仕組みをざっくりいうと次の通りです。
- P2Pネットワークを利用した「分散型台帳」技術で
- 数百、数千個の取引記録(トランザクション)をまとめたブロックを
- みんなで手分けして承認(マイニング)し
- 一本のチェーン(鎖)のかたちで共有する
はっきり言って意味不明ですよね。
詳しく深堀っていきます。
分散型台帳
ブロックチェーンはどこかのサーバーで一元管理されているわけではありません。
世界中の複数のコンピューターに全く同じ帳簿が保存されています。
個々のユーザー同士をネットワークで結んで、直接データをやり取りする「ピア・ツー・ピア(P2P)方式」を採用しています。
紙の帳簿に例えると、過去の取引が全部記載された帳簿があり、次に新しい取引がある程度溜まったら、別の紙に全部書き写して帳簿の最終ページに貼り付ける。
こうしてできた帳簿の最新バージョンを盗難防止のためコピーを何部か用意して、それぞれを別の場所に保管しておくイメージです。
実際の更新頻度は、取引が発生するたびに毎秒、数百回にわたってネットワーク上のすべてのコンピューターの帳簿を更新するのは不可能なので、10分毎にまとめて承認しています。
P2Pネットワークで管理、運営される取引記録があることから、ブロックチェーン=「分散型台帳」と呼ばれる理由です。
トランザクションとブロック
ビットコインの取引は世界中で24時間、365日行われています。
取引はすべてオープンになっていて、https://blockchain.com/explorerを見るとリアルタイムの更新が確認できます。
ただ、ビットコイン取引のはお互いに承認しあって初めて成立するので、この瞬間のすべての取引は「未承認」状態です。
そこでビットコインでは未承認のトランザクションをおよそ10分毎にまとめて一つの「ブロック」とし、一括して承認しています。
新規で承認されたブロックは承認済みのブロックを一続きにした一本のチェーン(鎖)の最後尾に追加されます。
これで初めて取引成立となります。
※正確に言うと手数料の高いトランザクションほど優先的に承認されるので、必ずしも取引順でブロックに格納されるわけではありあません。
マイニング
ブロックのつなげ方には規則があり、新規ブロックを最後尾につなげるには、規則に則った「鍵」を見つける必要があります。
この「鍵」を見つける作業を「マイニング(採掘)」といいます。
新たにブロックを追加するとき、「直前のブロックのハッシュ値(暗号化した値)+今回のブロックに含まれる全取引データ+任意の文字列」を64桁のハッシュ値に暗号化した上で、最初の19程度の文字列がすべて「0」になるような任意の文字列を見つけなければいけません。
つまりこの任意の文字列をしらみつぶしに調べる必要があります。
何億、何兆にも及ぶ試行錯誤をわずか10分で行うわけで、膨大なマシンパワーと電力が必要になるわけです。
ただ、ハイスペックなマシンを惜しげもなく投入したマイニング業者のほうが有利になります。
条件を満たす文字列を最初に見つけた人が勝者となり、その報酬として新たに発行されたビットコインがもらえるのです。
勝者は6.25ビットコインを得ることできます。
1BTC=500万 だとすると、約3125万円です。
この報酬が、賃料+マシン購入費+電気代などのコストを上回れば、それが利益になります。
マイニング専用マシンが高騰
マイングに特化した専用マシンには半導体が必要不可欠です。
しかし、スマホやパソコン、自動車を始め様々な機器にも半導体が搭載され、世界的な半導体不足が顕著になっています。
これが原因でマイニング機器の価格がどんどん高騰しているのです。
マニング企業が上場する理由
大手マイニング企業のナスダック市場への上場が相次いでいます。
なぜかというと上場すればマイニング報酬に加え、資本市場から資金調達できるようになり、さらにマニング機器への設備投資ができるからです。
このような流れがマイニング業界をよりパワーゲームの様相を呈するようになってきています。
つまりビットコインは順調に産業として育ってきているという見方もできそうです。
ブロックがつながる1本の鎖
ブロックにはおよそ10分ごとに承認されていくので、1時間で6個、1日で144個、1年で52560個のブロックが新たに追加されていきます。
2021年11月時点でブロック総数はおよそ71万です。
つまり、71万個のブロックが連なる枝分かれのないたった一本のチェーンに、過去のすべてのビットコイン取引の記録が残されているのです。
ブロックがチェーン上に繋がっているから「ブロックチェーン」というわけです。
ビットコインが抱える問題
ここまでビットコインが優れたテクノロジーの産物であることが分かったかと思います。
ただ、理想的な基軸通貨になるにはまだ解決しなければいけない課題があります。
・価格の変動が大き過ぎる
・マイニングコストが高過ぎる
・意思決定に時間がかかり過ぎる
当初の想定以上に急速に普及したことで、ビットコインには未解決の問題がこれだけあるのです。
それぞれ解説します。
処理時間がかかり過ぎる
ビットコインのマイニングは10分ごとに行われますが、1ブロックに書き込める取引数は限られています。
今後もビットコインユーザーが増え、取引量が増えるほど承認までの時間がかかってしまいます。
例えばビットコインを送金処理した場合、こちらはとっくに送金したのに承認されるまでに1時間以上かかってしまうと送金先の相手からはまだ届かないといった事態になってしまいますよね。
そこで解決策として次の3つの試みが登場しています。
- ブロックサイズを増やす
- 取引データの圧縮
- ブロックに書き込む取引数の絞り込み
それぞれの仕組みについては専門的でマニアックな話になるのでここでは割愛します。
この先もまだまだマイニングマシンのスペックが向上していくことからも、処理時間の問題は解消するでしょう。
なぜならブロックチェーン技術の優位性でもある「早くて安い」送金ができなくては、ビットコインの価値はなくなってしまうからです。
価格の変動が大き過ぎる
ビットコイン人気が高まり大量のマネーが流入してくると、ビットコイン価格の変動幅(ボラティリティ)が非常に大きくなります。
例えば要人のツイートや発言、世界情勢の動向で価格が大きく乱高下してしまいます。
数時間で10%以上も価格が変動すると取り扱いが難しく、投資先としての安定が担保できません。
そこで変動幅を抑えて価格を安定させるために、1ドル=1コインとして交換できるステーブルコインが登場しています。
米ドルに連動した代表的なステーブルコイン
- 2015年 テザー(USTD)
- 2018年 USDコイン(USDC)
- 2021年 ジーエン(GYEN)
しかしよく考えてみると1ドル=1コイン、つまりドルと同じ価値しかないのになぜこれらのステーブルコインを買うのでしょうか?
その理由は、ドルを持っているとマネーロンダリング対策もあり承認を得たり手続きが煩雑で手数料も高い。
だからと言ってビットコインでは変動幅が大きすぎて使い勝手がいいとはいえない。
そこでその中間的な存在のステーブルコインにニーズが出てきたわけです。
マイニングコストが高過ぎる
ビットコインのマイニングレースに勝利するために消費される電力は、年間100テラワットアワー(世界全体の電力量のおよそ0.5%)を超えるとも言われています。
この問題はSDGs(持続可能な開発目標)に反しており、「脱炭素」を目指す動きに逆行していると批判の対象となっています。
解決策は?
ビットコイン推進派、例えばツイッターCEOのジャック・ドーシーは2030年までに二酸化炭素の排出力を実質0にする計画で、ビットコインのマイニングが再生可能エネルギーとの親和性が高いといったレポートを発表しています。
とはいえ大量の電気が必要な状況は変わりはありません。
そこで解決策として、プルーフ・オブ・ワーク(※)というマイニングの仕組みを廃止して、別の承認プロセスを採用したコインが誕生します。
チェーンの最後尾に繋ぐための「鍵」をしらみつぶしに調べる処理方法
銀行間ネットワークで使用される「リップル」がそれです。
リップルとは?
リップルは低電力、低コストだけではなく、即時決済と価格の安定を同時に実現した優秀なコインです。
ビットコインにしても、ステーブルコインにしても一般ユーザーの売買を前提に設計されていますが、このリップルは銀行同士を繋ぐネットワークシステムです。
途上国の銀行システムや、国際送金システム(SWIFT)を保管し、アップデートする狙いもあります。
なので資産というよりも、現金と現金の間をつなげる「デジタル通貨」といったイメージです。
意思決定に時間がかかり過ぎる
ビットコインは国や組織など管理主体がありません。
このため参加メンバーによる話し合いでルールを決める必要があるわけです。
ところが利害関係者が増えると、いろいろな考えを持った人が入ってきて一つの方向に議論をまとめるのが難しくなりますよね。
結果的に意思決定に時間を要することになります。
しかし、この問題の解決策は簡単で、コインの発行や運営を管理する企業や団体がいればすみます。
ビットコインのような「分散型」ではなく、「中央集権型」であれば、意思決定はスムーズです。
すでにステーブルコインやリップルも真ん中に組織があって、開発計画や価格をコントロールしています。
ただ、今後ビットコインも中央集権型になるのかというと、それは無いと予想できます。
なぜならビットコインは分散型だからこそ、誰にもコントロールされず、改ざんできないという、そこに資産価値が見い出されたコインだからです。
まとめ
いかがでしたか?
ビットコインとブロックチェーンの概要がわかったのではないでしょうか。
この記事では、初心者向けに「ビットコイン」と「ブロックチェーン」について解説しました。
最後に内容をざっとおさらいしましょう!
ビットコインとは
- 【仮想通貨】実体の無いバーチャルなお金
- 【デジタル通貨】持ち運び自由の電子データ
- 【国際通貨】国に属さない通貨
- 【分散型通貨】民主的な運用とP2Pネットワーク
- 【暗号通貨】暗号を解く鍵がないと送金できない台帳技術
- 【暗号資産】投資対象として魅力あふれる資産
ブロックチェーンとは
- P2Pネットワークを利用した「分散型台帳」技術で
- 数百、数千個の取引記録(トランザクション)をまとめたブロックを
- みんなで手分けして承認(マイニング)し
- 一本のチェーン(鎖)のかたちで共有する
本記事を読んだ方はおそらくこれからビットコイン投資を始めようとしているはず。
あくまで自己責任でお願いしますが、次のステップは実際にビットコインを買ってみることをおすすめします。
ぼくは実際にビットコインを買ったことで、値動きに連動する出来事はなにか?など、勉強するようになりました。
やはりリアルの市場に身を投じるのが株やFXと同じで一番勉強できますね。
あくまで個人的推測ですが、長期的に見てビット金価格は10万ドルを超えると信じて投資しています。
今後も売らずにコツコツ買い増ししていきます。
最後まで読んでくださりありがとうございました!