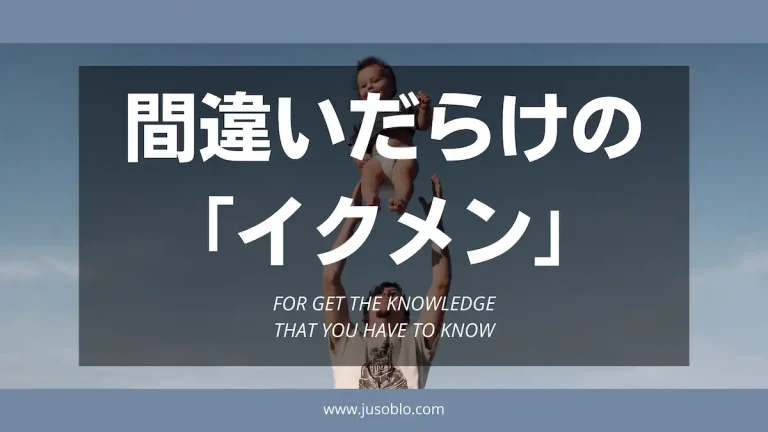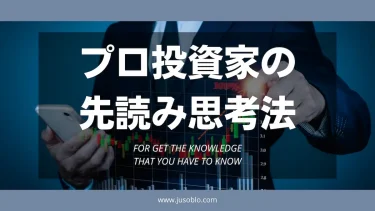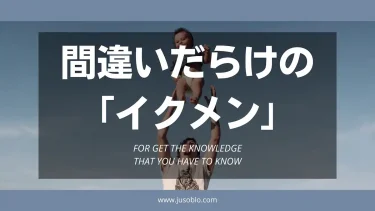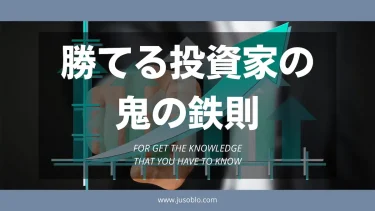こんにちは、jusonです。
知識の定着にコミットする「再読!今日の一冊」。
本日の一冊はこちら。
・あるべき父親像って?
・父親として何を教えたらいいの?
・子供のためになる子育てってどんなん?
・父親、母親それぞれの役割は?
本書はこんな悩みに答えてくれます。
本記事は、
- 読破した本の要点を
- 可能な限り短文にして
- 短時間で再読できる
備忘録です。
本記事を読むことで、未読の方もしれっと知ったかできるレベルまでインプットできるはず。
また、知識を定着させるには、本を再読することをお勧めします。
知識の定着に再読が必要な理由については、こちらの記事からどうぞ。
それでは、サクッと行きましょう!
第1章 イクメンへの疑問
国が推奨する「イクメン」の真意
国がイクメンを推奨するのは夫婦平等に子育てを負担させ、少子化に歯止めをかけるため。
より多くの子供を持ってね、というメッセージだけで、どう育てるべきか、どう育てていったら良いかについてはノータッチ。
父親の子育て参加のメリット
子育てにおける父親の影響力に関する調査の結果、父親が子育てに参加するほど母親の不安が少なくなる。
父親の子育て参加は、母親の自己閉塞感、加虐的態度を軽減する。
第2章 弱まる父性、強まる母性
父性原理とは?
- 義務を果たし能力を発揮するものだけを認め、それ以外は切り捨てる。
- 悪いことは厳しく叱り、頑張らないと叱咤激励し、適度に突き放し自立へと駆り立てる。
- 社会性のある自立した強い人間に育て上げる建設的な面と、あまりに厳しく切断の力が強すぎて破壊に至る面を持つ。
子供に張り付き甲斐甲斐しく世話をすると父性機能を発揮できない。
父性は、社会で直面する課題を乗り越える力を身に付けるように導くこと。
父親の役割
母親が「ありのまま」を受容するのに対して、父親は「こうあるべき」という規範を植え付ける役割を担う。
父親はあるべき姿を示し、鍛える役割を担っており、子供自身もそれを感じ取っている。
父性機能を発揮する父親になるには、時には「ダメだ!」といって動かない「壁」のような存在になるべき。
子供が3歳になる頃から、母性機能中心のサポートから、母性機能に父性機能を織り交ぜたサポートに切り替える必要がある。
第3章 小学生の暴力と父親の役割
なぜ小学生が暴力的?
小学校での暴力行為発生件数が、2013年に高校を抜き、とうとう2018年には中学校を抜き、2019年には高校の6.6倍になっている。
問題行動の発生理由
「児童に自分をコントロールする力がみについていない」
「児童の自己中心的傾向が強い」
EQの必要性
乳幼児期に重要なのは、非認知能力(EQ:心の知能指数)をしっかり身につけること。
非認知能力の核となる自己コントロール力が、人生の成功を大きく左右する。
32年間の追跡調査の結果、自己コントロール力が高いほど大人になってからの健康度が高く、集収入が高く、犯罪を犯すことが低い。
アメリカを真似る日本
知的能力ばかり重視してきたアメリカでは、いくらIQが高くても自己コントロール力が高くなければ社会的に成功できないと言われだしている。
日本ではせっかく自己コントロール力を重視する教育が行われてきたのに、それを軽視し、アメリカ流の自己主張の教育にシフトする動きさえみられる。
そもそも欧米人は心理学的調査でも攻撃性がることがわかっている。
これだけ文化的背景が違えば、教育のやり方に違いが出るのが当然で、真似ればいいということではない。
悪化する父親イメージ
男女ともに30年ほどの間に父親イメージが明らかに悪化している。
特に女子においては、1990年から2018年までに、父親に対するイメージが悪化傾向にある。
一般的に子供と過ごす時間の長い母親の父親に対する感情は、日頃の何気ない態度や言動が子供に伝わる。
父親への不満は子供にぶつけるのではなく、夫婦の語り合いの場で直接伝えるべき。
こどもを巻き込んではいけない。
自然と触れ合う必要性
最近は自然に触れることが少ないためか、昆虫を怖がる子供が多い。
2012年、ジャポニカ学習帳の表紙から昆虫写真が消えた。
自然体験の乏しさを補う上でも、父親の遊びを通した貢献が求められる。
自然体験の豊かな人ほど自尊感情(自己肯定感)が高い傾向が見られる。
第4章 日本の父親は子育てをしなかった?
なぜ父親は育児から遠のいた?
殆どの父親がサラリーマン化したから父親不在の状況が生まれた。
原因は、大資本が小売店を買収し店舗が大型化、食材分離が進み、多くの父親たちは自営業形態から働きに出るサラリーマン化していったから。
江戸時代は「父親が子供を育てた時代」。
家の継承に価値のある時代だったため、子育ては公(おおやけ)ごとであり、子育てこそが家の最高責任者たる男の責任だった。
豊かさの象徴「専業主婦」
専業主婦とは夫の収入のみで生計が成り立たない限り成立しない存在。
つまり裕福な家庭の妻のみのあり方。
社会全体が豊かになり、専業主婦は日本でも次第に大衆化していった。
子供を自立へと向かわせ、健全な発達を促すには、保護する母性と、厳しく鍛える父性、親として両方の心理機能を発揮することが求められる。
第5章 子供を鍛えられるのは親しかいない
父親はなにを教えるべきか?
まだ社会性を身に着けていない子供には、自由を尊重するより、まずは社会のルールを教える必要がある。
単に優しいパパは、職場に置き換えると、部下を叱責する場面できちんと指導できない上司と同じ。
そうしたパパに育てられた子供は、社会性や自己コントロール力が身についていないため、将来社会適応に苦労することになる。
欧米と日本の教育の違い
欧米では小学校でも能力が低ければ留年が当たり前で、成績が基準に達しなければ即座に切り捨てる。
「可愛そうだから」といって温情で進級させる日本とは大違い。
親は子供に譲歩しない欧米社会とでは、褒めることの意味、そして効果も違って当然。
このような文化的な違いを踏まえず、「アメリカは進んでいる」と海外流に追随するからおかしなことになる。
子供を導くためにすること
過保護に育てると傷ついて立ち直る経験が乏しくなる。
多少傷を負ったほうが子供の心は鍛えられ、社会化されていく。
子供が思い通りにならずイライラする母親が多いのは、父親が父性的役割を引き受けてくれないところが大きい。
父親として子供を導くためのヒント
- 挨拶、お礼を言うこと
- 我慢すること
- 簡単に諦めないこと、粘ること
- 相手の気持を想像する習慣をみにつけること
- いろんな友達と遊ぶこと
- 結果を気にせず挑戦すること
- 読書習慣を身に付け、好奇心をもつこと
- 働く姿を見ること、知ること